-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
2025年4月 日 月 火 水 木 金 土 « 3月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
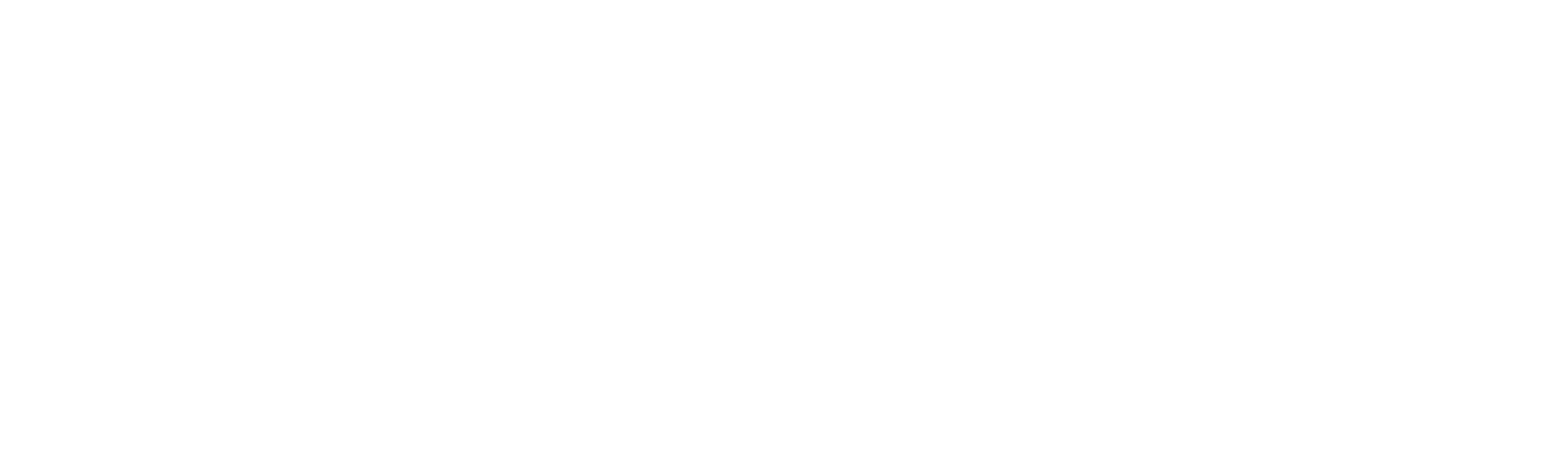
皆さんこんにちは!
株式会社RYUSENの更新担当中西です♪
今回のテーマは
SDG’sとリサイクル
ということで、産業廃棄物のリサイクルがSDGsとどのように関係し、企業がどのように取り組むべきかを深掘りしていきます♪
産業廃棄物の適正処理とリサイクル は、SDGs(持続可能な開発目標)の達成に不可欠な要素です。日本では年間約3.7億トン(2020年環境省統計)の産業廃棄物が発生しており、その処理と再利用は環境負荷の低減だけでなく、経済活動の持続可能性にも直結しています。
目次
SDGsの中で、産業廃棄物のリサイクルと深く関わる目標には、次のようなものがあります。
企業が産業廃棄物の適正処理とリサイクルを進めることは、これらのSDGs目標達成に大きく貢献します。
日本では、産業廃棄物の発生量は減少傾向にありますが、それでも年間約3.7億トンが発生しています。
そのうち、約50%はリサイクル・再利用されていますが、まだ多くが焼却や埋立処理に頼っている のが現状です。
産業廃棄物の主な種類
| 廃棄物の種類 | 例 | 主なリサイクル方法 |
|---|---|---|
| 金属くず | 建設廃材、自動車部品 | 再溶解・リサイクル金属として再利用 |
| 廃プラスチック | 工場の包装材、機械部品 | 再生プラスチック、燃料化 |
| 建設廃材 | コンクリート、アスファルト | 再生骨材、道路舗装材 |
| 食品廃棄物 | 食品加工工場の廃棄物 | 堆肥化、バイオガス発電 |
このように、産業廃棄物の種類に応じたリサイクル技術を活用することで、持続可能な社会の実現が可能になります。
3Rを積極的に推進 することで、廃棄物の発生量を抑え、環境負荷を削減できます。
企業事例:パナソニック
パナソニックは、工場で発生する廃プラスチックをリサイクルし、自社製品の材料として再利用する「循環型モノづくり」を推進。
近年、産業廃棄物のリサイクル技術が進化しています。
企業事例:トヨタ自動車
トヨタは、使用済みの自動車部品を回収し、リサイクル素材として再利用する「トヨタ・リサイクル・ビジョン」を展開。
企業事例:日本製紙
日本製紙は、紙のリサイクル率を向上させるため、使用済みの紙の回収ネットワークを構築し、トレーサビリティを確保。
産業廃棄物のリサイクルは、SDGs目標達成に向けた鍵となるだけでなく、企業の競争力強化にもつながります。
直線型経済(作る→使う→捨てる)から、循環型経済(使う→再利用→新たな資源へ) への移行が求められます。
SDGsの観点から、消費者は「環境配慮型企業」を評価する傾向が強まっています。
リサイクルへの積極的な取り組みは、企業ブランド価値を向上させます。
産業廃棄物のリサイクルは、企業にとってコスト削減・環境貢献・ブランド向上 の三拍子揃った戦略です。
SDGsを意識した企業の取り組みは、持続可能な未来を築くための第一歩 です。
あなたの企業は、産業廃棄物のリサイクルにどう取り組んでいますか?
今こそ、行動を起こす時です!
お問い合わせは↓をタップ
皆さんこんにちは!
株式会社RYUSENの更新担当中西です♪
今回のテーマは
SDG’sの企業努力について
ということで、企業がSDGsにどのように取り組むべきか、成功事例とともに深掘りしていきます♪
近年、SDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標) が企業活動において不可欠な要素となっています。単なるCSR(企業の社会的責任)としてではなく、企業の成長戦略の一環としてSDGsを組み込むことが求められています。
目次
SDGsは、「地球規模の課題を解決しながら、持続可能な成長を実現する」 という目的のもと、国連が2015年に掲げた17の目標です。これには、環境問題、貧困削減、ジェンダー平等、経済成長などが含まれます。企業は、単なる営利活動だけでなく、社会や環境に配慮した経営が求められるようになりました。
特に、以下のような理由からSDGsの取り組みが重要視されています。
企業がSDGsを意識した経営をするには、どのような行動が求められるのでしょうか?以下に、特に重要なポイントをまとめました。
環境問題への対応は、最も注目されるSDGsの一つです。企業は以下のような取り組みを行うべきでしょう。
企業事例:ユニリーバ
ユニリーバは、製品のライフサイクル全体で環境負荷を減らす「サステナブル・リビング・プラン」を推進。パッケージの再利用可能化や、カーボンニュートラルな生産を実施しています。
企業は、従業員の働きがいやダイバーシティ(多様性)を意識した環境作りを進めることが求められます。
企業事例:花王
花王は、女性のキャリア支援に積極的に取り組み、管理職の女性比率向上を目指しています。また、社員の働きがい向上のため、テレワーク制度やフレキシブルな働き方を導入。
企業は地域社会との連携を強化し、持続可能な社会を作る役割を果たすことも重要です。
企業事例:イオン
イオンは、地域農業の活性化に貢献する「トップバリュ グリーンアイ」を展開し、地元農家との連携を深めています。また、災害時の支援活動にも力を入れています。
SDGsへの取り組みは、数値化して評価することが重要です。企業は以下のような指標を活用し、成果を可視化するとよいでしょう。
企業事例:パタゴニア
アウトドアブランドのパタゴニアは、環境負荷を最小限にするための指標を設定し、すべての製品にリサイクル素材を使用するなど具体的な目標を達成しています。
SDGsは、企業にとって単なる義務ではなく、新たなビジネスチャンスを生む可能性を秘めています。消費者の意識が高まる中、「社会的課題の解決と利益の両立」 を実現する企業こそが、未来の市場で生き残るでしょう。
企業努力としてSDGsを取り入れることは、長期的な競争力を高める鍵となります。これからの企業経営において、持続可能性を意識した戦略を構築し、社会とともに成長する姿勢が求められています。
あなたの企業は、SDGsにどのように取り組んでいますか?
ぜひ、自社の取り組みを振り返り、未来への一歩を踏み出してみてください!
お問い合わせは↓をタップ
皆さんこんにちは!
株式会社RYUSENの更新担当中西です♪
今回のテーマは
なぜリユースが注目されている?!
ということでゼロエミッションについてご紹介します♪
環境問題が深刻化する中、日本でも「リユース(Reuse)」への関心が急速に高まっています。リユースは、「3R(リデュース、リユース、リサイクル)」の一環として、廃棄物を減らし、資源を有効活用するための重要な取り組みです。
近年、日本ではフリマアプリの普及や企業のサーキュラーエコノミー(循環型経済)へのシフトが進んでおり、リユース市場は拡大を続けています。本記事では、リユースの重要性、日本での最新の取り組み、そして今後の可能性について詳しく解説します。
目次
「リユース(Reuse)」とは、使い終わった製品をそのままの形で再利用すること を指します。これは「リサイクル(Recycle)」とは異なり、資源に戻して作り直すのではなく、できる限りそのままの状態で再利用することを目的としています。
🔹 リユースの具体例
日本では、環境意識の高まりに伴い「持続可能な消費」が求められています。その中で、リユースの価値が再評価され、次のような理由から注目されています。
ごみ削減と環境負荷の低減
経済的メリット
サステナブルなライフスタイルへのシフト
日本では、スマートフォンの普及とともにフリマアプリ市場が急拡大しました。特に、「メルカリ」や「ラクマ」などのサービスは、多くの消費者に利用されており、手軽に不用品を売買できるプラットフォームとして定着しています。
📌 メルカリの影響
中古スマートフォンやパソコンのリユース市場も成長しています。例えば、AppleやNTTドコモは、自社製品のリユース・リファービッシュ(整備済み製品の再販売)を推進し、環境負荷を低減する取り組みを進めています。
📌 日本のリユース家電市場の特徴
ファッション業界でも、リユースが進んでいます。H&Mやユニクロなどの大手ブランドは、不要になった衣類を回収し、リユースまたはリサイクルするプログラムを実施しています。また、ヴィンテージショップやリサイクルショップの人気も高まり、中古衣料の需要が増加しています。
📌 注目のリユースファッション
近年、日本では「所有する」から「共有する」へと意識が変わりつつあります。カーシェアリング、シェアオフィス、家具や家電のレンタルサービスなど、リユースの概念を活かしたビジネスモデルが増えています。
📌 日本で拡大するシェアリングサービス
リユースは、環境負荷を減らすだけでなく、私たちの生活を豊かにする可能性を秘めています。日本では、フリマアプリの普及やシェアリングサービスの発展により、リユースがより身近なものとなっています。
🌱 今日からできるリユース活動
✅ フリマアプリやリサイクルショップを活用する
✅ 不要なものを捨てずに誰かに譲る(寄付・リユース活動)
✅ シェアリングサービスを積極的に利用する
リユースの習慣を取り入れることで、持続可能な未来への一歩を踏み出しましょう! 🚀🌍
お問い合わせは↓をタップ
皆さんこんにちは!
株式会社RYUSENの更新担当中西です♪
今回のテーマは
3Rについて
ということでゼロエミッションについてご紹介します♪
近年、環境問題がますます深刻化する中で、リサイクル業界が果たす役割は非常に重要になっています。その中心にあるのが 「3R」 という考え方です。3Rとは、Reduce(リデュース)、Reuse(リユース)、Recycle(リサイクル) の3つの頭文字をとったもので、資源を大切にし、環境負荷を減らすための基本原則を表しています。
本記事では、3Rの具体的な意味とその重要性、さらに私たち一人ひとりが実践できる方法について詳しく解説します。
目次
「リデュース」とは、そもそも ごみを発生させない という考え方です。製品の過剰包装を避けたり、使い捨て製品を減らしたりすることで、ごみの発生を抑えることができます。
🔹 具体的な取り組み
「リユース」は、一度使ったものをそのまま再利用すること を指します。例えば、衣類や家具、電化製品などを捨てずにリユースすることで、資源の浪費を防ぐことができます。
🔹 具体的な取り組み
「リサイクル」は、使い終わったものを資源として再利用する ことを意味します。例えば、ペットボトルや古紙をリサイクルすることで、新たな製品の原材料として生まれ変わらせることができます。
🔹 具体的な取り組み
世界中で大量消費が進む中、ごみの量は増加し続けています。特に、プラスチックごみは深刻な問題で、海洋プラスチック汚染が生態系に大きな影響を及ぼしています。
また、廃棄物を処理するための焼却や埋立も環境負荷が高く、温室効果ガスの排出や土地の汚染を引き起こします。こうした問題を解決するために、3Rの取り組みが求められているのです。
私たちが日常的に使っている資源は有限です。特に、レアメタルや石油などの天然資源は、将来的に枯渇する可能性が指摘されています。リサイクルを推進することで、これらの資源を有効活用し、持続可能な社会を築くことができます。
3Rを推進することは、企業や個人にとっても経済的なメリットがあります。例えば、リサイクル素材を活用することで、原材料費を削減できるだけでなく、新たなビジネスチャンスを生み出すことも可能です。また、リユースやリペアを意識することで、無駄な出費を抑えることができます。
ヨーロッパでは、環境意識の高まりとともにリサイクル政策が進んでいます。特にドイツは「循環経済」のリーダーであり、リサイクル率が高い国の一つです。ドイツの「デュアルシステム」では、消費者が適切に分別したごみを回収し、リサイクル業者が資源として再活用する仕組みが整っています。
日本でも、プラスチックごみの削減や食品ロスの対策が進められています。例えば、「コンビニのレジ袋有料化」や「食品リサイクル法」の施行により、企業や消費者の意識が変わりつつあります。また、ペットボトルのリサイクル率が高く、世界的にも先進的な取り組みが評価されています。
世界的な企業も3Rに積極的に取り組んでいます。例えば、Apple は使用済みiPhoneの部品を回収・リサイクルし、新製品の原材料に再利用しています。また、ユニクロ では、不要になった衣類を回収し、難民支援などに役立てるプログラムを展開しています。
3Rは、政府や企業だけでなく、私たち一人ひとりの意識と行動が重要です。
✅ 買い物の際に意識すること
✅ 日常生活でできること
✅ 企業や社会との連携
3Rは、環境問題の解決だけでなく、経済や社会の持続可能性にも大きく貢献します。私たち一人ひとりが日常生活の中で意識を持ち、行動を変えることで、未来の地球を守ることができます。
「小さな一歩が、大きな変化を生む」
今日からできることを始めてみませんか? 🌱🌏
お問い合わせは↓をタップ
皆さんこんにちは!
株式会社RYUSENの更新担当中西です♪
今回のテーマは
ゼロエミッションって??
ということでゼロエミッションについてご紹介します♪
ゼロエミッション(Zero Emission)とは、人間の活動によって排出される廃棄物や汚染物質を可能な限りゼロに近づける概念です。これは単なる環境保護の取り組みではなく、持続可能な社会を実現するための根本的な考え方として注目されています。特に地球温暖化や資源枯渇といった問題が深刻化する中で、ゼロエミッションの重要性が高まっています。
目次
ゼロエミッションの概念は、1990年代に東京大学の研究グループが提唱しました。もともとは産業廃棄物を他の産業の資源として再利用し、廃棄物の発生をゼロにすることを目指したものです。その後、この考え方は企業や国際機関の間で広まり、現在では温室効果ガスの排出削減や資源循環の取り組みにも適用されています。
ゼロエミッションの目的は、以下の2つに集約されます
温室効果ガスの排出を抑えるために、再生可能エネルギーの利用が推進されています。太陽光発電や風力発電、水力発電などのクリーンエネルギーは、ゼロエミッションを実現する上で重要な役割を果たします。また、エネルギーの効率化や電気自動車の普及も、排出削減に貢献しています。
例:欧州連合(EU)は、2050年までにカーボンニュートラルを達成する計画を立て、再生可能エネルギーへの移行を進めています。
製造業では、廃棄物や副産物を他の業界で活用する「産業間連携」が進められています。また、製品設計の段階からリサイクル可能な素材を使用し、廃棄物の発生を抑える取り組みが行われています。
例:日本の製鉄業界では、製造過程で発生するスラグ(副産物)をセメント原料として再利用する技術が一般的です。
建設業界では、ゼロエミッションビルディング(ZEB)という取り組みが注目されています。ZEBは、建物のエネルギー消費を最小限に抑え、必要なエネルギーを再生可能エネルギーで賄う建築を指します。
例:世界各地でZEBが増加しており、特に北欧諸国では、エネルギー効率の高い建築技術が普及しています。
廃棄物を「ゴミ」として捨てるのではなく、再資源化することでゼロエミッションを実現する取り組みが進んでいます。分別収集やリサイクル技術の向上、バイオテクノロジーを利用した分解技術がその一例です。
例:ドイツは、廃棄物の分別収集とリサイクル率の向上において世界をリードしており、埋め立て廃棄物をほぼゼロにしています。
「スマートシティ」や「カーボンニュートラル都市」の構築も、ゼロエミッションの一環として進められています。これらの都市では、交通、エネルギー、廃棄物管理が効率化され、持続可能な生活を実現しています。
例:デンマークのコペンハーゲンは、2050年までに完全なゼロエミッション都市を目指しています。
自然環境への負荷を軽減し、生態系の維持に寄与します。特に、温室効果ガスの排出を減らすことは、地球温暖化の抑制に直結します。
廃棄物を資源として再利用することで、コスト削減や新たなビジネス機会が生まれます。また、エネルギー効率化によるコスト削減も期待されます。
持続可能な取り組みを進めることで、企業や地域のイメージが向上し、社会的な信頼が高まります。
ゼロエミッションの実現には、多くの課題が残されています。特に、技術革新が必要な分野や、コストの面での制約が挙げられます。また、発展途上国では、基盤となるインフラが整備されていない場合が多く、先進国との格差が課題となっています。
今後は、以下の点が重要になります
ゼロエミッションは、地球環境を守り、持続可能な社会を構築するための希望の鍵です。私たち一人ひとりが、エネルギー消費や廃棄物の削減に関心を持ち、行動に移すことで、より良い未来を創造することができます。政府や企業の取り組みだけでなく、私たちの生活の中での小さな工夫が、ゼロエミッション達成への大きな一歩となります。
お問い合わせは↓をタップ
皆さんこんにちは!
株式会社RYUSENの更新担当中西です♪
皆様新年あけましておめでとうございます!
今年も弊社【株式会社RYUSEN】への変わらぬご愛顧賜りますようお願いいたします。
さて2025年RYUSENの雑学講座開講です♪
今回のテーマは
産業廃棄物削減にむけた世界的な取り組みについてご紹介します♪
産業廃棄物は、製造業や建設業をはじめとする産業活動から生じる廃棄物であり、環境問題や資源の枯渇を引き起こす大きな要因です。この問題に対処するために、各国や国際機関、企業が多様な取り組みを進めています。
目次
産業廃棄物は、自然環境に悪影響を及ぼすだけでなく、埋め立て地の逼迫や有害物質の漏洩といった社会問題を引き起こします。また、廃棄物の処理には膨大なエネルギーやコストが必要であり、持続可能な社会の実現を阻害する要因となっています。そのため、産業廃棄物の削減は、環境負荷の軽減と経済の効率化の両面で非常に重要とされています。
世界各国で循環型経済が注目され、廃棄物を「資源」として捉える考え方が広がっています。製品設計の段階でリサイクル可能な材料を使用することや、製品寿命を延ばすためのメンテナンスサービスが重要視されています。
例えば、欧州連合(EU)は「循環経済行動計画」を策定し、資源効率を高めるための規制や支援策を導入しています。製品のリサイクル可能性を評価する基準を設け、企業に対してより持続可能な製造方法を促しています。
多くの国や企業が、廃棄物を全く出さない「ゼロエミッション」を目標に掲げています。これは、廃棄物を再利用やリサイクルによって価値ある資源に変換し、最終的な埋め立て処分をゼロにする取り組みです。
日本では、廃棄物処理法の強化とともに、ゼロエミッションを目指す企業が増えています。製造業の現場では、副産物や余剰材料を別の業界で活用する「産業間連携」が進められています。
廃棄物処理技術の進歩が、産業廃棄物削減に大きく貢献しています。特に、AIやIoTを活用した効率的な廃棄物管理や、バイオテクノロジーを活用した有害廃棄物の分解技術が注目されています。
例えば、中国ではAIを用いたリサイクル施設の導入が進み、廃棄物の分別や処理効率が大幅に向上しています。また、バイオプラスチックや分解性素材の研究開発が世界中で活発に行われています。
各国の政府や国際機関が産業廃棄物削減を目的とした政策や規制を強化しています。具体的には、廃棄物の分別収集の義務化や埋め立て廃棄物の量に対する課税などがあります。
アメリカでは、環境保護庁(EPA)が廃棄物削減プログラムを通じて企業の削減目標達成を支援しています。一方で、アフリカの一部の国々では、廃棄物輸出の受け入れを禁止する政策が採用され、不法廃棄の抑制に取り組んでいます。
国際連合(UN)や経済協力開発機構(OECD)などの国際機関は、廃棄物管理に関する知識や技術の共有を推進しています。特に、発展途上国では、廃棄物管理インフラが整っていないため、先進国との協力が重要です。
国連の「持続可能な開発目標(SDGs)」では、目標12「つくる責任、つかう責任」で廃棄物削減の重要性が明記されています。この目標達成に向けた各国の取り組みが加速しています。
多くの企業が、自社の廃棄物削減を進めるだけでなく、顧客やサプライチェーン全体にわたる取り組みを行っています。
産業廃棄物削減には多くの成功事例がある一方で、課題も残っています。特に、発展途上国では廃棄物管理インフラが整っておらず、不適切な処理が行われるケースが多いです。また、廃棄物削減を進める上でのコストや技術的な制約も依然として存在します。
今後は、国際的な協力を強化し、先進的な技術や知識を広く普及させることが求められます。同時に、個々の企業や消費者が廃棄物削減に積極的に取り組む姿勢が、持続可能な未来を築く鍵となります。
産業廃棄物の削減は、環境保護だけでなく、経済の効率化や社会の安定にも直結する重要な課題です。世界全体での協力と技術革新を通じて、この複雑な問題に対処していく必要があります。
お問い合わせは↓をタップ
皆さんこんにちは!
株式会社RYUSENの更新担当中西です♪
秋らしい北風が心地いい季節になりましたが、朝晩の冷え込みはとてつもないですね。。。
体調管理には皆様お気をつけください!
さて本日は
リサイクル雑学講座
ゼロウェイスト運動とは?海外での注目事例
ゼロウェイスト運動の歴史と基本理念
ゼロウェイスト運動は、20世紀後半から始まりました。この運動は、廃棄物を「削減する」だけでなく、「完全になくす」ことを目指します。これには、廃棄物を単なるゴミとしてではなく「資源」として再利用し、自然界の循環を模倣する経済システムを構築するという理念が含まれています。
基本理念
ゼロウェイスト運動は「3R(リデュース、リユース、リサイクル)」の考え方に基づいていますが、さらに「リフューズ(拒否)」や「リペア(修理)」を加えた「5R」や「6R」に発展しています。
廃棄物の排出を防ぐ(リフューズ、リデュース):過剰な消費や使い捨て文化を見直す。
リユースとリペア:既存の製品を修理し、再利用する文化を復興する。
リサイクルの推進:廃棄物を資源として活用。
歴史的背景
ゼロウェイストの概念は1990年代にカリフォルニア州の地方自治体で正式に提案され、その後、環境NGOや企業によって世界中に広まりました。
具体的な実践方法
リデュース、リユース、リサイクルの3R
リデュース(減らす)
最も重要なステップです。無駄な包装や使い捨て商品を避け、長期的に使える高品質な製品を選ぶことが求められます。
実例:スーパーでプラスチック袋を使わず、マイバッグを利用する。
政策例:欧州連合(EU)による使い捨てプラスチック製品の禁止。
リユース(再利用する)
再利用可能な製品を選び、一度使用したものを新たな目的で使う。
実例:リターナブルボトルや再利用可能な金属製ストローの普及。
商業活動:リサイクルショップやフリーマーケットの活用。
リサイクル(再資源化する)
廃棄物を分別し、資源として再利用できる状態にする。
実例:ドイツのデポジットシステム(Pfand)では、リサイクル可能なボトルを返却すると返金されます。
挑戦点:リサイクル可能な材料が限られているため、リサイクル率を高めるための技術革新が必要です。
海外で成功している事例や企業の取り組み
ゼロウェイストを実現した都市
サンフランシスコ(アメリカ)
サンフランシスコは2002年に「ゼロウェイスト」目標を設定し、2020年までに廃棄物の100%再利用を目指しました。この都市は、以下の取り組みで廃棄物リサイクル率を80%以上に達成しました
全住民と事業者に対するリサイクルの義務化。
生ゴミを堆肥化するプログラムを導入。
コペンハーゲン(デンマーク)
コペンハーゲンは、廃棄物をエネルギーに変換する最新技術を活用し、焼却処理時のエネルギー回収効率を高めています。また、リサイクル施設の設置が進められ、プラスチックの90%以上がリサイクルされています。
廃棄物削減をビジネスモデルに組み込む企業
ループ(Loop)
パッケージを完全に再利用可能にするためのプラットフォームを提供。消費者は製品を購入した後、使用済みパッケージを返却し、企業が清掃して再利用します。
テラサイクル(TerraCycle)
リサイクルが難しい製品を再資源化するプログラムを提供しています。使用済みの歯ブラシや化粧品容器などの回収を促進し、それを新たな製品に変換します。
パタゴニア(Patagonia)
衣料品を長く使うことを奨励し、製品の修理サービスを提供。消費者に不要になった製品を回収し、リサイクルするプログラムも運営しています。
消費者レベルでのゼロウェイストライフスタイル
ゼロウェイスト運動は、個人のライフスタイルにも影響を与えています。
包装を減らす
地元の市場や「バルクショップ」で必要な分だけ商品を購入し、包装材を最小限にする。
例:ガラス容器を持参して食品を詰める。
再利用可能なアイテムの利用
再利用可能な水筒やタンブラーを使用。
布製の袋やメッシュバッグで食品や野菜を持ち帰る。
手作りや修理文化の復興
古くなった製品を修理して再利用し、不要なものは寄付や販売をする。
デジタル化の活用
紙の消費を減らすため、電子請求書や電子書籍を活用。
ゼロウェイスト運動の未来
ゼロウェイスト運動は、単なる環境保護活動としてではなく、持続可能な経済への移行を目指すグローバルな潮流となっています。この運動の拡大は、政府、企業、個人の協力が欠かせません。より多くの地域での成功事例が増えることで、ゼロウェイスト社会の実現はさらに近づくでしょう。
次回のシリーズでは、食品廃棄物削減と持続可能なフードシステムについて掘り下げます。
皆さんこんにちは!
株式会社RYUSENの更新担当中西です♪
秋らしい北風が心地いい季節になりましたが、朝晩の冷え込みはとてつもないですね。。。
体調管理には皆様お気をつけください!
さて本日は
リサイクル雑学講座③
廃棄物問題の現状とその影響
世界的な廃棄物危機の現状
現代社会では、経済発展と人口増加に伴い廃棄物が急増しています。国連の報告によると、世界中で年間20億トン以上の廃棄物が発生しており、そのうち33%が適切に処理されていないと言われています。この未処理の廃棄物は、特に低所得国で深刻な環境問題を引き起こしています。
プラスチック廃棄物
プラスチック製品は、その便利さから世界中で広く使われていますが、廃棄物の大部分を占めています。毎年800万トン以上のプラスチックが海洋に流れ込み、2050年には魚の重量を超えると言われています。プラスチックは分解に数百年を要するため、環境に長期間残り、生態系を脅かしています。
食品廃棄物
世界で生産される食品の約3分の1(年間約13億トン)が廃棄されています。食品廃棄物の大部分は埋め立て地で分解し、メタンガスを発生させて地球温暖化を促進します。この問題は、食糧不足や貧困といった社会問題とも密接に関連しています。
電子廃棄物
年々増加する電子廃棄物(E-waste)は、2021年には5700万トンに達しました。使い捨て文化やテクノロジーの急速な進化が、この増加を後押ししています。これらの廃棄物は適切に処理されないと、有害物質が環境や人々の健康に悪影響を与えます。
廃棄物が環境、生態系、人間の健康に与える影響
環境への影響
廃棄物は、土壌、水質、大気に深刻な汚染をもたらします。例えば、埋め立て地から浸出する有害化学物質は地下水を汚染し、長期的に自然環境を破壊します。また、廃棄物の焼却は温室効果ガスを大量に排出し、地球温暖化を悪化させます。
生態系への影響
海洋に流れ込むプラスチック廃棄物は、魚や海鳥などの生物が誤って摂取することで健康被害を引き起こします。また、マイクロプラスチックは食物連鎖を通じて人間の体内にも取り込まれる可能性があります。
人間の健康への影響
不適切に処理された廃棄物は、直接的または間接的に人々の健康に悪影響を与えます。例えば、電子廃棄物に含まれる鉛や水銀などの有害物質が土壌や水を汚染し、それを摂取した住民に健康被害をもたらす可能性があります。
廃棄物の種類とその増加傾向
廃棄物は、大きく以下のように分類されます。
一般廃棄物(家庭ゴミ)
紙類、食品廃棄物、プラスチック、ガラスなどが含まれます。
産業廃棄物
製造業や建設業から出る廃棄物で、重金属や有害物質を含む場合が多いです。
医療廃棄物
病院や医療施設から排出される感染性廃棄物など。
これらの廃棄物は世界中で増加傾向にあり、特に都市化が進む地域で問題が深刻化しています。
特定地域での問題点
アジア地域
発展途上国では、廃棄物の適切な管理インフラが不足していることが多く、焼却や不法投棄が一般的です。これにより大気汚染や水質汚染が拡大しています。
海洋環境
太平洋ゴミベルト(Great Pacific Garbage Patch)は、海流に乗った廃棄物が集まり、巨大なプラスチックの「島」を形成しています。これにより海洋生物への深刻な影響が懸念されています。
先進国のリサイクル危機
中国が2018年に廃プラスチックの輸入を禁止したことで、アメリカやヨーロッパ諸国はリサイクルの危機に直面しています。
世界各地で注目されている廃棄物関連の政策やニュース
欧州連合(EU)
EUは「サーキュラーエコノミー」への移行を目指し、使い捨てプラスチック製品の禁止やリサイクル率向上の目標を設定しています。
フランス
食品廃棄禁止法を導入し、スーパーでの食品廃棄を防止する取り組みを進めています。
アフリカ
ルワンダやケニアなどではプラスチック袋の使用が禁止され、持続可能な代替品の普及を推進しています。
この章では、廃棄物問題の全体像とその深刻さを知ることで、私たち一人ひとりが行動を起こすきっかけを提供します。次回のシリーズでは、廃棄物削減に向けた具体的な取り組みを探ります。
皆さんこんにちは!
株式会社RYUSENの更新担当中西です♪
秋らしい北風が心地いい季節になりましたが、朝晩の冷え込みはとてつもないですね。。。
体調管理には皆様お気をつけください!
さて本日は
リサイクル雑学講座③
SDG’s~つかう責任・つくる責任~
ということで、本記事では、この課題について深掘りし、その重要性や取り組み事例を紹介します♪
持続可能な開発目標(SDGs)の12番目に掲げられている「つくる責任、使う責任」は、私たちの消費と生産の在り方を見直し、地球環境や社会的課題に配慮した経済活動を促進するものです。このテーマは、日々の生活から企業活動に至るまで、多くの場面で深く関わる目標です。
目次
この目標は、消費と生産のパターンを持続可能な形に変えることを目的としています。これには以下の要素が含まれます:
地球が供給できる資源には限りがあります。例えば、石油や金属鉱物などは、現在の消費速度ではいずれ枯渇する可能性があります。また、森林伐採や水資源の過剰使用は、環境破壊を引き起こします。
特にプラスチックゴミや食品廃棄物は深刻な問題です。プラスチックは分解に数百年かかり、海洋生態系に悪影響を及ぼします。一方で、食品ロスは約3分の1の食料が無駄になるという統計があり、多くの人々が飢えに苦しむ中で重大な倫理的問題を抱えています。
無駄な消費や大量生産は温室効果ガスの排出を増加させ、気候変動を加速させます。この影響は、私たちの生活や将来の世代に深刻な結果をもたらします。
「つくる責任、使う責任」を実現することは、地球環境だけでなく、社会全体の福祉向上にも繋がります。一人ひとりが小さな行動を積み重ねることで、大きな変化を生み出すことが可能です。私たちは今こそ、未来世代のために責任ある選択をしなければなりません。
次回リサイクル雑学講座④もお楽しみに♪
皆さんこんにちは!
株式会社RYUSENの更新担当中西です♪
秋らしい北風が心地いい季節になりましたが、朝晩の冷え込みはとてつもないですね。。。
体調管理には皆様お気をつけください!
さて本日は
リサイクル雑学講座②
~産業廃棄物における歴史~
弊社、株式会社RYUSENでは産業廃棄物におけるリサイクルを主に行っております。そこで産業廃棄物の歴史をご紹介し、日本において環境意識の高まりや公害問題の解決策として発展してきた、その歴史を今日は見ていきたいと思います!
目次
1960年代の日本では、高度経済成長期に伴う産業活動の増加により、大量の産業廃棄物が発生し、深刻な公害問題が顕在化しました。四大公害病(イタイイタイ病、水俣病、四日市ぜんそく、新潟水俣病)に象徴されるように、産業廃棄物の不適切な処理が住民の健康や環境に大きな影響を与えていたため、社会問題として取り上げられるようになりました。
1970年代に入ると、政府は産業廃棄物の管理・処理に関する法整備を進め、1970年には「廃棄物処理法」が制定されました。この法律により、事業者には産業廃棄物の適切な処理責任が課されるようになり、廃棄物の収集や運搬、処理に関する基準が設けられました。この頃から、産業廃棄物のリサイクルも徐々に注目され始めましたが、まだ廃棄物の適正処理が優先されていた時代です。
1980年代になると、資源不足や環境問題の意識がさらに高まり、リサイクルの重要性が認識され始めました。この時代には、特に建設業や製造業で発生する廃棄物の再利用が注目され、廃棄物の減量や再利用を目的とした取り組みが進みました。例えば、コンクリートやアスファルトの破片を再利用する「建設リサイクル」や、鉄・非鉄金属のリサイクルが盛んに行われるようになりました。
1990年代には、地球環境問題への意識がさらに高まり、産業廃棄物のリサイクルが重要な施策となりました。特に1991年に制定された「リサイクル法(資源の有効な利用の促進に関する法律)」により、特定の産業廃棄物について再利用を義務づける規制が強化されました。これにより、産業廃棄物をリサイクルするための技術開発や処理施設の整備が進み、循環型社会の構築に向けた取り組みが本格化しました。
2000年代に入ると、「循環型社会形成推進基本法」や「建設リサイクル法」などの法整備が進められ、リサイクルがさらに推進されました。また、企業の間では「ゼロエミッション」や「グリーン調達」など、廃棄物の発生を抑えつつリサイクル率を高める取り組みが広がりました。リサイクル技術も高度化し、プラスチックや電子機器、バイオマスなど、さまざまな廃棄物のリサイクルが可能になりました。
現在では、持続可能な社会の構築をめざし、産業廃棄物のリサイクルはSDGs(持続可能な開発目標)達成の一環として重要なテーマとなっています。製品の設計段階からリサイクルを考慮した「デザイン・フォー・リサイクル」や、IoT技術を用いた廃棄物管理の効率化が進んでいます。さらに、カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みとして、産業廃棄物からエネルギーを回収する「サーマルリサイクル」や、廃棄物を原料とする循環型の「バイオリサイクル」も注目されています。
このように、日本では産業廃棄物のリサイクルが公害対策から始まり、循環型社会の実現をめざした取り組みへと進展してきました。
産業廃棄物は一歩間違えると多くの人の人生を左右してしまう大きな問題へとつながります。
少しでも多くの人の人生を幸せにする!
大切なお仕事です。
次回リサイクル雑学講座③もお楽しみに♪
![]()